広島で育った私にとって、毎年8月6日は特別な一日です。 今年は被爆から80年。節目のこの日に、今考えていることを個人的な気持ちとして記しておこうと思います。
広島で育つなかで、原爆のことは決して「遠い過去の出来事」ではありませんでした。
身近な祖父母や親戚から当時の話を聞く機会は多くありました。親戚に限らず、学校の教員、近所のお年寄り、習い事の先生、入院中に同室だった方など、日常生活のいろいろな場面で、原爆の体験を語ってくださる方が身近にいました。家族からは「職場でこんな体験を聞いたよ」と話してもらうこともありましたし、クラスでも「うちの曾祖父母、祖父母はこういう体験をした」と自然に話し合うような雰囲気がありました。夏休みの宿題で「原爆の体験を身近な人に聞いてこよう」という課題が出ることもあり、それは特別なことではありませんでした。
幼稚園には、被爆当時の遺物が飾られていて、小さい頃は絵本や歌を通して、成長するにつれては資料や手記を読みながら、原爆や平和について学びました。
小中高を通して、毎年1~2度は「平和週間」が設けられ、千羽鶴をクラスで分担して折ったり、卒業生や学校に縁のある方々が「語り部」として訪問してくださったりしました。
校内には、原爆で亡くなった数百人の生徒や教職員を悼む慰霊碑が建てられており、通学路にも、慰霊碑や被爆当時のまま保存された井戸などが残されていました。
街を歩くと慰霊碑は点在していて、私自身は数回ですが、何も書かれていない川や建物に、静かに手を合わせている方の姿を見たこともあります。
校内活動ではありますが、署名板を持って核廃絶を訴える署名活動に自ら参加したこともあります。また、修学旅行では長崎や沖縄を訪れ、広島とは異なる戦争の記憶や、日本が加害者として関わった歴史について学ぶ機会もありました。授業では、戦争の話だけでなく、「平和の実現」はまず目の前の日常生活――いじめや争い、差別をなくすことから始まるのだと教えられることもありました。けれど、そうした理念を語りながらも、それとは矛盾する現実に、憤りや違和感を覚えることもありました。
戦争や平和について考えることは、私にとって決して教科書の中のことではなく、日常のすぐ隣にあるものでした。
そうした環境で育った私は、「核兵器は絶対に持ってはいけない」「日本が持つなんてとんでもない」という価値観を、ごく自然なものとして受け取ってきました。
しかし、転校で2年間市外の学校に通ったとき、市内に比べて平和教育が少ないことに驚きました。そして大学生になって県外に出て暮らしてみると、「日本も核兵器を持つべきだ」と当たり前の顔をして話す人や、投下時間はおろか、8月6日という日付すら覚えていない人に出会い、大きな衝撃を受けました。
私は今の時点で、現代の「核保有」の是非について語れるほどの知識は持っていません。
たしかに、現代の社会情勢や、実際に核の傘下にある現状を踏まえると、理想だけでは難しいという考えがあることも理解しています。
それでも、理想を掲げ続ける人の存在も、そして個人的な体験を語り継ぐことも、やはり重要なのではないかと思います。
「理想主義だ」と切り捨てるのではなく、現実の声と理想とをともに共有したうえでこそ、議論に意味が生まれると感じます。
今後、核が存在する限り、人為的な判断だけでなく、偶発的なリスクも背負うことになる。そのことも忘れずに議論すべきだと考えています。
ただ、自分の価値観の根底には、広島で聞き続けてきた体験があり、その一つ一つが重く残っています。これからも、自分なりに学び、考え続けていきたいと思っています。
伝えるほどの新しさはないかもしれませんが、あらためて心に浮かんだ2つのことを、ここに残しておきます。
もちろん、どんな戦争にも言えることではありますが、「多くの人が亡くなった」という一言で済ませてはいけないと思っています。失われたのは、単なる「命の数」ではありません。それぞれが歩んでいた、かけがえのない人生でした。それは、他でもない人の手で引き起こされました。
無機質にワンクリックでデータを消去するように消えたのではなく、火傷や熱で苦しみながら亡くなった方、放射線の影響で健康を害し続けた方、その方々のみならず、その家族や友人のその後の人生が大きく狂わされました。そして、その人たちが将来持つはずだった大きな幸せも小さなかけがえのない時間も、友人や同僚との関係も仕事としての成果も、将来持つ可能性があった家庭や子ども、孫といった命のつながりも、何もかも断たれてしまいました。
そしてもう一つ、決して目を背けてはいけないのは、原爆が都市そのものを標的にし、主目的が「民間人の大量殺傷」であったという事実です。
たとえ表向きには「軍事施設の破壊」「戦争の早期終結」と言われても、実際には都市を選び、多数の非戦闘員を狙ったものでした。犠牲になった多くは、戦地に行っていなかった女性や子ども、建物疎開や軍需工場などに動員されていた中高生、高齢者、そして障害のある方々でした。また、日本人だけでなく、朝鮮半島や中国、アメリカなど海外の方々も多く亡くなりました。動植物、街並みや文化財といった造形物も、何もかも被害を受けました。原爆投下は、明らかに「都市への攻撃」であり、核の威力を確かめる「人体実験」を兼ねた非人道的な行為でした。
そうした事実に目を向け、語り継がれた体験に耳を傾け続けること。
私自身、その意味を問い続けながら、広島で育った一人として、これからも向き合っていきたいと思っています。
そして今後も、自分なりに学びを続けながら、さまざまな立場の人々と対話していけたらと考えています。
2025年8月6日 赤木奏映
(写真:2022年12月29日筆者撮影)





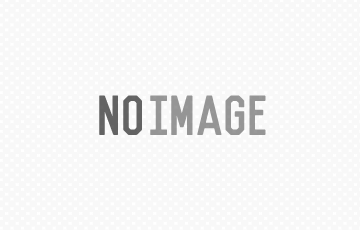
コメントを残す